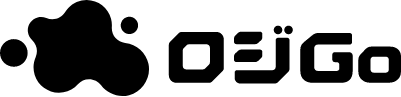データ活用が物流を変える。活用までの壁を突破するDXの進め方
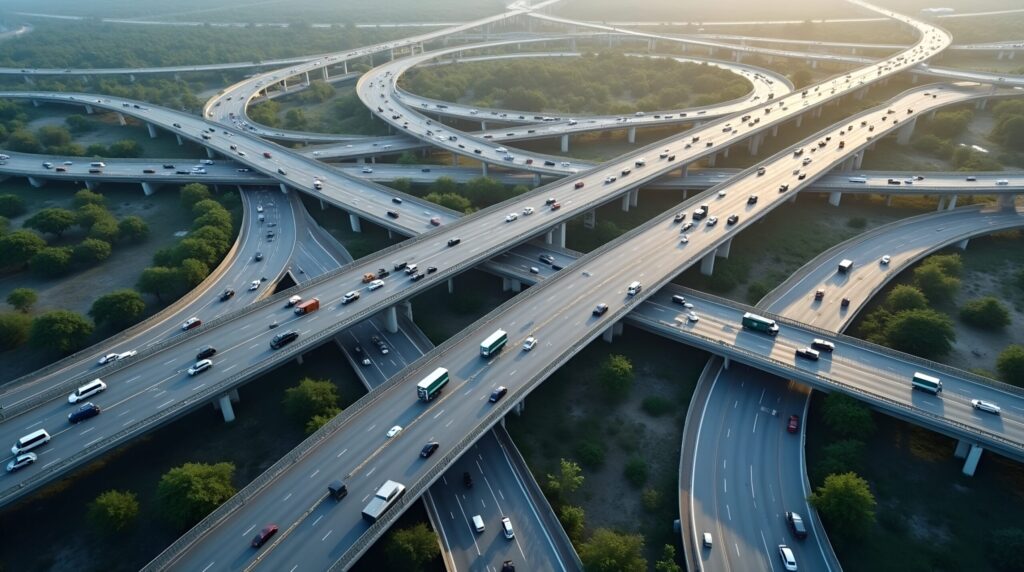
データ活用は、物流ビジネスそのものを変革する力があります。本記事では、データ活用の具体的な効果と手法を、多くの企業が陥りがちな課題と成功事例を交えながら解説させていただきます。
- 1. 【結論】データ活用の成否は現場オペレーションとの連携で決まる
- 2. データはあるのに活用できない2つの理由
- 2.1. 増改築を重ね、サイロ化したレガシーシステム
- 2.2. データ活用の前に「整理」で力尽きる、非効率な手作業
- 3. データ活用以前の課題:アナログ管理が内包する潜在的経営リスク
- 3.1. 業務ノウハウの非資産化と、属人化による事業継続リスク
- 4. 【課題解決事例】データ活用がもたらす4つの変革
- 4.1. 【業務の標準化】属人化した配車から「データ主導の最適配車」へ
- 4.2. 【コストの可視化】"経験と勘"から脱却し、データを運賃交渉の武器に
- 4.3. 【業務プロセスの自動化】リスクの高い手入力作業をゼロに
- 4.4. 【基盤システムの刷新】変化を恐れる組織から、DXを推進する組織へ
- 5. データ活用の第一歩。何から始めるべきか?
- 5.1. Step1:課題の設定
- 5.2. Step2:データ資産の整理と課題の特定
- 5.3. Step3:スモールスタート(PoC)と効果測定
- 6. 成功の鍵を握るパートナー(ベンダー)選定のポイント
- 6.1. 「現場」の機微を理解する、業界特化の深い知見
- 6.2. 物流業界の「実務データ」を扱った実績と経験値
- 6.3. 多様な現場との「折り合い」を乗り越える「伴走力」
- 7. 【まとめ】データ活用で実現する「全ての荷物が届く当たり前の世界」
【結論】データ活用の成否は現場オペレーションとの連携で決まる
なぜ、多くの企業が最新ツールを導入してもデータ活用に失敗するのか。その答えは、多くのプロジェクトで「データと現場が繋がっていない」からです。
物流データを可視化しすることで現場オペレーションの課題解決につながる。データから現場の課題を読み解き、データを基に具体的なアクションを構築する。それが物流データ活用成否の鍵と言えるでしょう。
具体的にはどういうことでしょうか。この記事では物流の現場での事例から、確実な成果を生み出すステップを解説します。
データはあるのに活用できない2つの理由

「データ活用の重要性は理解している」「TMS(Transport Management System 輸配送管理システム)や受発注システムなど、データを蓄積する仕組みも既にある」。しかし、いざ「運行別の収益性を分析したい」と思っても、すぐに答えは出てきません。その原因はどこにあるのでしょうか。
増改築を重ね、サイロ化したレガシーシステム
多くの企業では、長年の事業活動の中で各部署が必要なシステムを異なるベンダーから導入してきた経緯があります。結果、複数のシステムが複雑に絡み合い、データが各所に点在・サイロ化。どのシステムに、どのようなデータが、どんな形式で保存されているのか、全体像を把握することさえ困難な状況にあるのです。
データ活用の前に「整理」で力尽きる、非効率な手作業
サイロ化、点在化したデータを活用しようとすると、各システムの担当者へ個別に依頼し、出力された複数のExcelファイルを手作業で突き合わせる…といった非効率な作業が発生。これではデータを「活用」する以前に、「整理する」だけで力尽きてしまうでしょう。この「宝の持ち腐れ」状態が、データ活用の大きな障壁となっているのです。
データ活用以前の課題:アナログ管理が内包する潜在的経営リスク
「そもそも活用できるデータがない」。多くの企業では、今もExcelや電話、FAXによるアナログな業務が中心となっているのが実情です。一見、問題なく遂行できているように見えるその業務プロセスには、企業の成長を阻害する深刻なリスクが内包されています。
業務ノウハウの非資産化と、属人化による事業継続リスク
Excelや手作業による業務では、配車ノウハウといった貴重な情報が組織のナレッジとして蓄積されません。全ての判断が個人の経験則に依存するため、担当者の退職が事業停滞に直結する「属人化」のリスクを常に抱えることになります。日々生まれるデータは資産化されることなく散逸し、組織の成長機会を逸し続けているのです。
【課題解決事例】データ活用がもたらす4つの変革

データを真の経営資源に変えた企業は、どのような変革を実現しているのでしょうか。具体的な課題解決のパターンと、関連する企業事例をセットでご紹介。
【業務の標準化】属人化した配車から「データ主導の最適配車」へ
- 課題:
- ベテラン担当者の勘と経験則で配車が組まれ、属人化による技術継承リスクも高い。
- 解決策:
- 実績データや車両情報、ドライバーの勤務状況を基に、最適な配車計画を自動で算出。誰が担当しても効率的な配車が可能となり、コスト削減に直結。
- 関連事例:
- 大手卸A社は、過去の配送実績等を統合的に分析。日々の波動に合わせた効率的な配送計画の自動策定を可能にし、オペレーションの標準化とコスト削減を実現。
【コストの可視化】"経験と勘"から脱却し、データを運賃交渉の武器に
- 課題:
- 車両別・案件別の正確な収益性が分からず、感覚で受注判断をし、不採算案件も受注してしまっている。
- 解決策:
- 運行における実運送コストと売上を正確に把握。不採算案件を特定し、運賃交渉の場で客観的なデータを提示することが可能に。
- 関連事例:
- 大手元請け企業B社は、各種データを統合・可視化するデータ基盤を構築。データに基づいた収益管理と効率的な配送計画により、競合他社との差別化を実現。
【業務プロセスの自動化】リスクの高い手入力作業をゼロに
- 課題:
- 紙からExcel、Excelからシステムへの手入力がなくならず、人件費はかさみ、ミスや入力漏れのリスクも高い。
- 解決策:
- データ基盤の構築により、手作業で行っていたデータ収集・加工作業を自動化。担当者は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。
- 関連事例:
- 中小元請け企業C社は、EC案件増大に伴い、依頼データの一括自動処理システムを構築。工数を大幅に削減し、パートナー会社とのリアルタイム連携を実現。
【基盤システムの刷新】変化を恐れる組織から、DXを推進する組織へ
- 課題:
- 増改築を繰り返したレガシーシステムが原因で、新システム導入時の影響範囲が不明瞭。関係各所が変化を恐れ、DXが進まない。
- 解決策:
- 業務を熟知したベンダーと伴走しながら、社内に散在するデータを一元化。データ基盤の構築は、単なるIT導入ではなく、組織変革のきっかけとなります。
- 関連事例:
- 大手倉庫業D社は、増改築を繰り返ししたシステムに加え、各拠点でシステムの入力ルールや、商材の特性の差異により統一化が難しい状況でした。導入効果の理解浸透から、時間をかけて伴走することでシステム統一化を実現。
データ活用の第一歩。何から始めるべきか?

具体的なデータ活用イメージに続いて、データ活用プロジェクトの進め方を3ステップで解説します。
Step1:課題の設定
データ活用を成功させる秘訣は「データありき」よりも「課題ありき」のスタートをおすすめします。まず「何のためにデータを活用するのか」という目的を明確にし、そこから具体的な「積載率30%向上」「実車率20%向上」などの目標を設定していきます。そうするとデータの過不足が明らかになり、適切な計画を設定できます。
Step2:データ資産の整理と課題の特定
H3:Step2:データ資産の整理と課題の特定
次に、Step1で決めた課題を分析・解決するために必要なデータが、社内のどこに、どのような形式で存在しているかを可視化します(データ資産の棚卸し)。この段階ではデータを集める必要はなく、まずデータの在り処と取得方法を地図のように描き出すことが重要です。
Step3:スモールスタート(PoC)と効果測定
いきなり全社的なシステム導入を目指すのではなく、まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)として、最小単位でデータの有効性を証明します。特定の運行に絞り、Step2で特定したデータを手作業でも良いので集計・分析し、「データを使えば、これだけの改善が見込める」という成果を作ることが重要です。
成功の鍵を握るパートナー(ベンダー)選定のポイント

冒頭で述べた通り、データ活用の成功は「データと現場が繋がるか」で決まります。これは、パートナー(ベンダー)選びにおいても、揺るぎない判断基準となります。
最新のツールや機能を比較検討するだけでは十分ではなく、本質を見誤るかもしれません。本当に大事なのは、「そのベンダーは、あなたの会社のデータと現場を真に繋ぐことができるのか?」という一点です。そのための選定ポイントを3つの視点から解説します。
「現場」の機微を理解する、業界特化の深い知見
データ分析の前提として、ベンダー自身が物流の現場を深く理解していることが不可欠です。データに現れる数字の裏には、配車担当者の判断、ドライバーの業務実態、業界特有の商習慣といった、無数の「現場の機微」が隠されています。こうしてデータが「意味のある情報」へと解像度が高くなります。
物流業界の「実務データ」を扱った実績と経験値
一口に物流と言っても、その内実は千差万別です。企業の規模や、扱う商材によって、求められるオペレーションや商慣習は全く異なります。この多様性は、そのままデータの構造や意味の複雑さに直結します。成功パターンが、別の物流会社では通用しないことも珍しくありません。だからこそ、単一の成功体験だけではなく、様々な業態の物流企業を支援してきた中で培われた「知見の幅」が、パートナーの真価を測る上で極めて重要です。
多様な現場との「折り合い」を乗り越える「伴走力」
「データと現場の繋がり」は、システムを導入すれば自動的に完成するものではありません。言葉で言うのは簡単ですが、拠点が違えばルールも扱う商材も全く異なるのが物流会社です。そのため、導入プロセスでは多様な現場の要求と、システムの標準機能との間で、必ず難しい調整(折り合い)が必要になります。この複雑なプロセスから逃げずに、現場の責任者から担当者まで多くのステークホルダーと向き合い、導入までの道を一緒に走ってくれるか。それが求められる「伴走力」です。
【まとめ】データ活用で実現する「全ての荷物が届く当たり前の世界」

データ活用が物流の未来をどう変え、適切なパートナーと確実な一歩を踏み出すことが不可欠であると解説してきました。
私たちが日々享受している「注文した荷物が、当たり前のように届く世界」。この未来にわたって維持・発展させるため、データという新たな資源を最大限に活用することが不可欠です。
大量のデータ処理と分析を得意とするシマントは、業界知識豊富なメンバーと多くの物流会社様を支援してきました。その実績と経験を駆使して、物流の未来を支える皆様の挑戦を全力でサポートいたします。もし皆様がデータ活用という経営課題に対し、共に悩み、共に汗を流せるパートナーを必要とされているなら、ぜひ一度シマントにお声がけください。