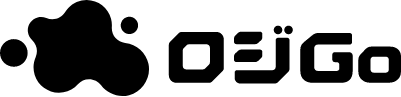物流コンサルタントとは?その役割と経営にもたらす価値

物流コンサルタントとは、企業の物流・サプライチェーンが抱える課題を、専門的な知見から解決に導く物流に特化した改善・改革の専門家です。
単に「物を運ぶ」だけでなく、DX推進や現場オペレーションも視野に入れ、サプライチェーン全体の改革戦略を実現するまで伴走することが、彼らのミッションです。
本記事では、物流コンサルタントの具体的な仕事内容から、失敗しない選び方、そしてコンサル導入でビジネスを拡大するための要点を解説します。
- 1. 複雑化する経営課題に応える、3つの提供価値
- 1.1. ①データに基づく現状分析
- 1.2. ②課題の特定から解決策の提案
- 1.3. ③解決策の実行・定着支援
- 2. 物流コンサルタントが提供する具体的な支援内容
- 2.1. 【戦略・企画領域】
- 2.2. 【業務・現場改善領域】
- 2.3. 【IT・システム領域】
- 3. 物流コンサル依頼。失敗例と予防策
- 3.1. 「現場の解像度が低い提案」となり、現場のコンセンサスを得られない
- 3.2. 「報告書がゴール」になってしまう
- 3.3. 「データ不足」により解決策が仮説だらけに
- 4. 物流コンサル導入の前にやるべきこと
- 4.1. データの収集と整理
- 4.1.1. ①コスト関連データ
- 4.1.2. ②オペレーション関連データ
- 4.1.3. ③ 各種マスタデータ
- 5. サプライチェーンの全体最適がなぜ大事なのか
- 5.1. なぜ、「全体最適」の1歩目は「部分最適」ではないのか
- 6. 物流コンサルの価値を最大化させるシステムとは
- 6.1. シマントが提供するAuto Dispatchが描く未来の物流
複雑化する経営課題に応える、3つの提供価値

物流コンサルタントは、物流戦略の策定から現場オペレーションの改善まで、客観的な第三者の立場で企業と伴走します。企業価値そのものを向上させるための変革を支援するプロフェッショナルと言えます。
①データに基づく現状分析
物流コンサルタントの仕事は、まず客観的な事実把握からはじまります。輸配送コスト、在庫データ、倉庫作業データといった定量的な情報の収集だけではなく分析可能な「使えるデータ」に整備することが重要です。加えて、現場スタッフへのヒアリングなど定性的な情報を組み合わせ、現状の物流オペレーションをわかりやすく可視化します。
②課題の特定から解決策の提案
現状分析で得られた客観的なデータ(ファクト)を基に、コスト増の根本原因となっている課題を特定します。そして、特定された課題に対し、原因を深掘りし、輸配送ネットワークの再設計、ITシステムの導入、倉庫レイアウトの変更といった、具体的で実現可能な解決策を策定・提案します。
③解決策の実行・定着支援
優れたコンサルタントの仕事は、提案で終わるのではなく、その解決策が具体的な「成果」に結びつくまでの変革を支援することです。主に以下のようなサポートを行うことが多いです。
・プロジェクトの進捗管理:
計画通りに施策が進むよう、スケジュールや課題を管理します。
・部門間の調整、合意形成:
各部門の利害調整の助言を行い、改革がスムーズに進むようステークホルダーとの合意形成の支援を行います。
・新しいオペレーションの定着支援:
新しい業務プロセスが組織に根付くための仕組みを提案します。
これらの活動を通じて、最終的に当初設定した目標数字を達成し、クライアントの経営戦略の実現に貢献します。
物流コンサルタントが提供する具体的な支援内容
物流コンサルタントの支援領域は、企業の課題に応じて多岐にわたります。ここでは代表的な支援内容を3つの領域に分けてご紹介します。
ご紹介する3つの領域は、相互に密接に関わり合っており、切り離して考えることはできません。重要なのは、これら「戦略」「業務」「IT」を三位一体で捉える視点です。これら全てを網羅し、最終的に経営インパクトへと繋げることができるコンサルタントが求められています。ここでは、物流コンサルの支援内容の一例をご紹介いたします。
【戦略・企画領域】
・物流戦略の策定・再構築: 経営戦略と連動した、中長期的な物流戦略を策定。
・サプライチェーン全体の最適化: 調達・生産・物流・販売までの一連のプロセスを可視化し、全体の最適化を図ります。
・物流DX構想の策定: 最新技術の活用を見据え、企業の物流DX化に向けたロードマップを作成します。
【業務・現場改善領域】
・配車業務の最適化と、輸送アセットの価値最大化:
属人的な配車業務から脱却し、誰でも最適な計画を組めるデータに基づいた業務プロセスへと変革します。この新しいプロセスを土台に、動態管理データを活用した実車率の向上や、協力会社ネットワークによる帰り便の確保といった施策を実行。トラックやドライバーといった輸配送アセットの価値を最大化し、輸送コストの削減と収益性の向上を両立させます。
・在庫管理の最適化:
高精度な需要予測モデルを構築し、それに基づき調達から在庫補充までをコントロールすることで、欠品による販売機会損失と過剰在庫を削減します。これにより、保管・廃棄コストが削減されるだけでなく、突発的な緊急輸送の発生を抑制し、輸配送計画全体の安定化にも貢献します。
【IT・システム領域】
・TMS(輸送管理システム Transportation Management System)、WMS(倉庫管理システム Warehouse Management System)、請求管理等のシステム選定・導入支援: 企業の課題に最適な物流関連システムの選定から、導入・定着までを支援します。
・輸配送ネットワークDX化支援:
自社の車両だけでなく、協力会社の車両も含めた輸配送ネットワーク全体のデジタル化を支援します。アナログなやり取りをプラットフォーム化し、求荷求車情報をデータ連携することで、最適な輸送手段を効率的に確保する仕組みを構築します。
・マテハン・自動化機器の導入支援: ロボットや自動倉庫など、省人化・効率化に繋がるマテリアルハンドリング機器の導入をサポートします。
物流コンサル依頼。失敗例と予防策

物流コンサルタントへの依頼は、大きな投資です。しかし、その活用方法を誤ると、期待した成果が得られないばかりか、高額な費用が無駄になるケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンとその具体的な予防策を解説します。
「現場の解像度が低い提案」となり、現場のコンセンサスを得られない
・失敗パターン:コンサルタントが経営層との対話のみで、倉庫や配送センターといった「現場」の実態を深く理解しないまま、理想論に基づいた提案をしてしまうケース。提案内容が現実的でなければ、現場スタッフの協力や合意(コンセンサス)を得られず、改革は絵に描いた餅で終わってしまいます。
・予防策:提案だけでなく、実行と定着までを支援する「ハンズオン型」のコンサルタントを選ぶことが重要です。契約前に、コンサルタントがどれだけ現場でのヒアリングや実態調査、業界知識を重視しているかを確認し、プロジェクト体制に現場のキーマンを巻き込むことを依頼しましょう。
「報告書がゴール」になってしまう
失敗パターン:分厚く体裁の整った分析報告書が納品され、プロジェクトが完了となってしまうケース。報告書の内容がいかに優れていても、それが具体的なアクションに繋がらなければ、組織は何も変わりません。
予防策:依頼する側が、プロジェクトのゴールを「報告書の受領」ではなく、「コストXX%削減」や「リードタイム〇日短縮」といった、測定可能な成果(KPI)に設定することが重要です。契約段階で、成果の定義と、そこまでの具体的な実行支援を要件に含めて依頼しましょう。
「データ不足」により解決策が仮説だらけに
失敗パターン:社内にデータが散在していたり、そもそもデータが取得できていなかったりするために、コンサルタントが客観的な分析を行えず、「おそらくこうだろう」という仮説に基づいた、説得力のない提案しかできないケースです。
予防策:まず、自社のデータを整理・可視化し、分析の土台となる「ファクト」を固めることが重要です。この土台がなければ、いかに優秀なコンサルタントでも的確な分析はできず、その提案はデータに基づかない仮定を基にした「仮説」に終わってしまいます。まず自社のデータに向き合うことが成功の鍵となります。
物流コンサル導入の前にやるべきこと

コンサルタントの価値を最大化するためには、依頼する側の「準備」も非常に重要です。社内で取り組んでおくべきことを解説します。
データの収集と整理
物流改革の第一歩は、現状を客観的に把握するための「データ収集と整理(データマネジメント)」であり、これはコンサルタントがその専門性を発揮する重要な領域です。
依頼する側の準備として、事前に「どこに、どのようなデータがあるか」の見当をつけておくだけでも、プロジェクトの精度とスピードは大きく向上します。もしくは「データがどこにあるかわからない」ことが「わかった状態」でも十分な進歩です。
コンサルタントとの協業をよりスムーズで実りあるものにするための「準備」として、以下のデータ領域について、まずは社内で議論を始めておくことをお勧めします。
①コスト関連データ
・項目例: 輸送費(チャーター、路線、宅配便など)、保管費、荷役費、包装費、人件費
・ポイント: 勘定科目上の総額だけでなく、可能な限り「拠点別」「商品カテゴリ別」「荷主別」など、多角的に分析できるよう内訳を整理しておくことが望ましい。
②オペレーション関連データ
・項目例: 出荷件数・数量、在庫日数、ピッキング件数・行数、誤出荷率、トラックの積載率・実車率
・ポイント: 物流品質、コスト、納期を示す主要なKPIを時系列で追えるようにしておくことで、課題の特定が容易になります。
③ 各種マスタデータ
・項目例: 商品マスタ、拠点マスタ(倉庫・店舗など)、顧客・納品先マスタ
・ポイント: これらのマスタデータが、コストやオペレーションデータと紐づけられる状態にあることが理想です。これにより、「SKU別の採算性分析」など、より高度な分析が可能になります。
サプライチェーンの全体最適がなぜ大事なのか
サプライチェーンの全体最適とは、製造・在庫管理・配送・販売までの一連のプロセス(サプライチェーン)を、個別の機能の集合体としてではなく、一つの統合された流れとして管理し、全体の効率性と収益性を最大化することです。
それを実現するための第一歩は自社の現状を客観的なデータで正確に把握すること。各部門に散在する販売データ、在庫データ、輸配送データなどを一元的に収集・整理し、分析できる状態にしておくこと。この土台が不完全であると、一箇所のプロセスを変更したとしても、その影響がサプライチェーンの他領域にどう波及するのかを正しく把握できません。結果として、自部門の範囲内での改善に留まり、意図せずして「部分最適」の判断を繰り返してしまうのです。この土台があって初めて、サプライチェーン全体の課題を可視化し、効果的な打ち手を検討することが可能になります。
なぜ、「全体最適」の1歩目は「部分最適」ではないのか
各部門が自部門のKPI達成のために行った改善が、会社全体の不利益に繋がってしまう。これが「部分最適」の罠です。例えば、調達部門がコスト削減のために大量一括購入をすれば、物流部門では保管コストと在庫リスクが増大します。各部門の努力を真の企業価値向上に繋げるには、部門の壁を越えた「全体最適」の視点が不可欠なのです。
物流コンサルの価値を最大化させるシステムとは

物流コンサルタントが描いた高度な輸配送戦略は、確かなデータに基づき策定されなければいけません。シマントの「Auto Dispatch」はそれを可能にする大量データ処理ロジックです。
シマントが提供するAuto Dispatchが描く未来の物流
シマントが開発した配車システム「Auto Dispatch」は自社配送の効率化と共同配送を推進し運行効率の向上を実現させる大量データ処理ロジックです。大量の輸配送案件から最適な組み合わせを自動計算し、結果として配車計画の時間を大幅に短縮します。配送計画を行う実務者の業務効率化はもちろん、走行距離や車両台数の最適化によるコスト抑制、CO2排出量の低減によるESG経営への貢献といった、明確な経営メリットを創出します。
シマントと「Auto Dispatch」は、貴社とコンサルタントが目指す、データドリブンな未来の物流経営達成を支援します。